思いを託すむずかしさ
ある山間(やまあい)の町でコンサートをしたときのこと。
打ち合わせの際、主催者の方が神妙な顔で相談があるとおっしゃるので、何事かと聞いてみると、近くにしゃれた花屋がないので、演奏後、舞台で花束を渡すことができない、と。
「なぁんだ、そんなことか」である。
演奏した後、舞台でお花をいただくのはうれしいが、なくてはならないものではない。演奏が終わると、頭の中はほとんどからっぽで、お花をいただかなくても、「あれ、今日はお花がないな」などとは、正直一度も思ったことがない。だから、お花をいただいてうれしいという気持ちはあっても、ないから失礼、ということは、全くないのである。花束を持って出てこられる方が、緊張しておられると、気の毒になるくらいのものだ。
「お花はなくても大丈夫です。それに、旅先ですから次の日までもたせるのも大変です。」と言ったのだが、それでも、気になる様子。
「それならば、野に咲く花を一輪摘んでいただけるなら、なによりの贅沢です」と申し上げた。でも、その贅沢さの感覚は、どうも相手に伝わらなかったようで、スタッフの間でいろいろと相談してくださったのだろう、お花の代わりにと舞台に登場したのは、「地酒」であった。
人は、お祝いやお礼の気持ち、時には弔意を花に託すのだが、人に花を贈るのは本当にむずかしい。この間も、「これは芸能人御用達のなんとか(カタカナの難しい名前)という店に注文したものです」と贈ってくださったが、どうもすましこんでいるようで、うちのような長屋住まいには、似つかわしくないように思えた。同じように「都会の匂い」がする立派なお花でも「うちの娘が東京で花屋をやっておりまして」と、お嬢さんが奮闘しておられる様子がうかがえる手紙付きのものは、花も生き生きとうちに馴染んでくれるような気がした。これは全く見るものの勝手で、花に罪はないのだけれど。
思えば、「花より団子」という言い回しがあるくらい。花に気持ちを込めるという風流は、昔からの難題なのかもしれない。
(朝日新聞 京都版 2007年9月28日掲載 「風知草」全8回より 第3回)



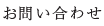
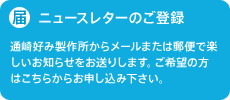
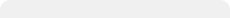
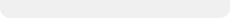
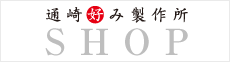
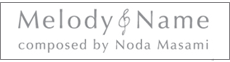

 通崎睦美
通崎睦美 製作所スタッフ
製作所スタッフ



