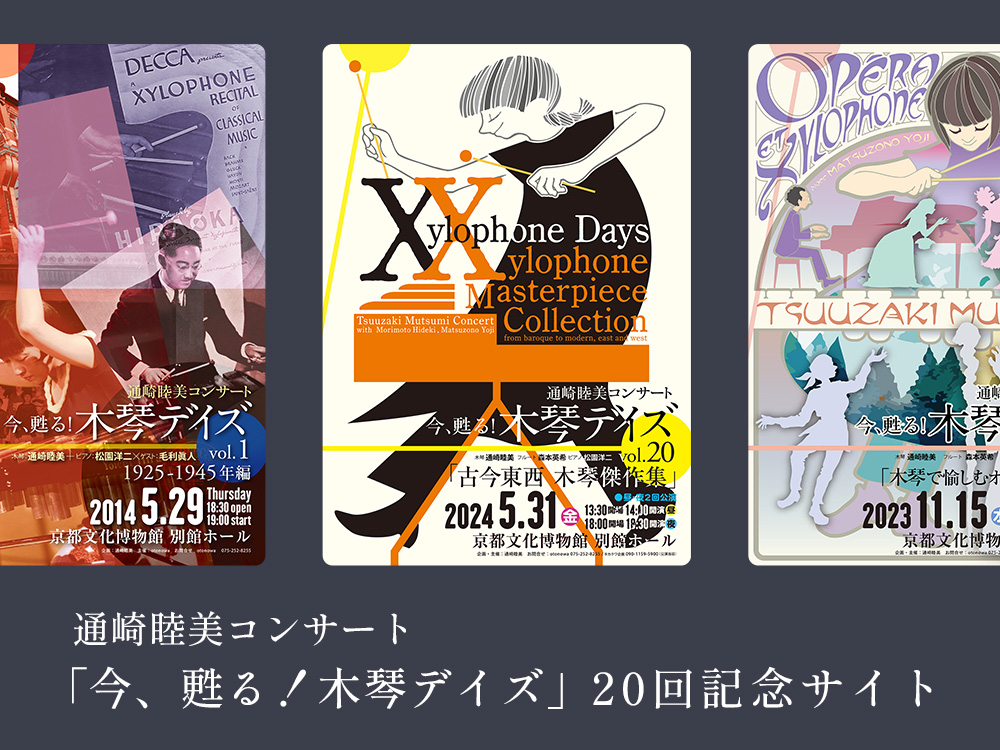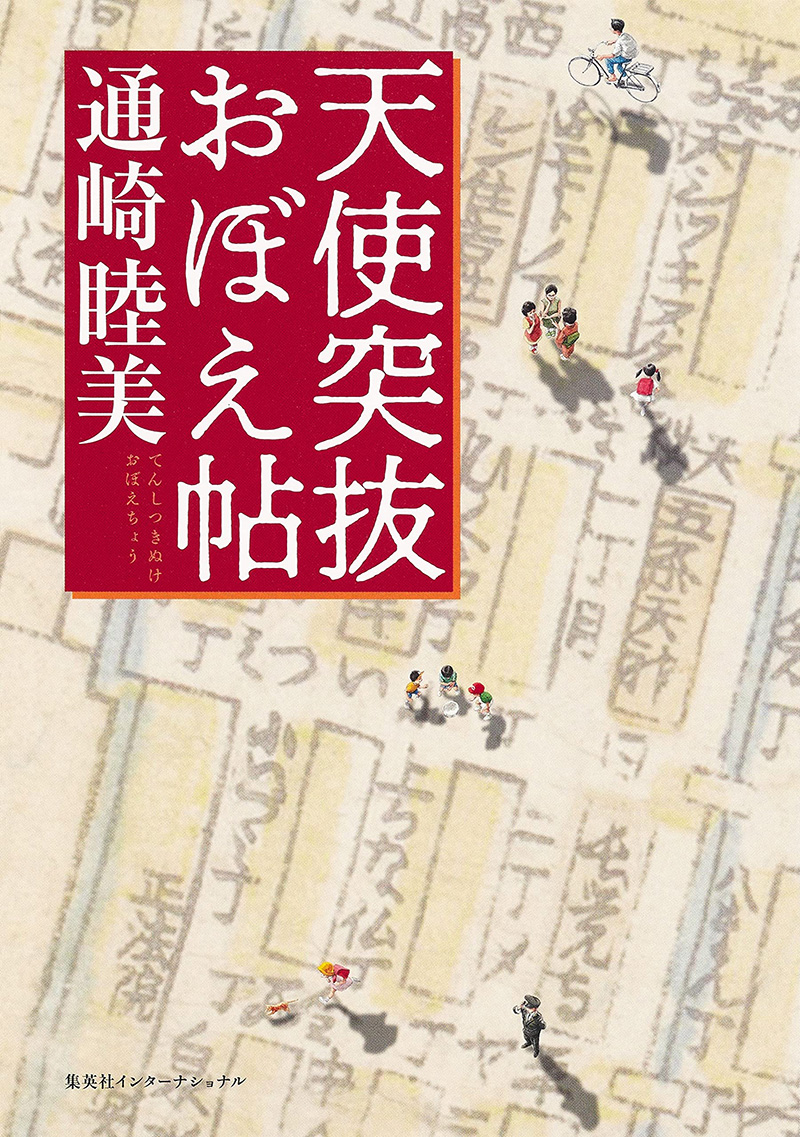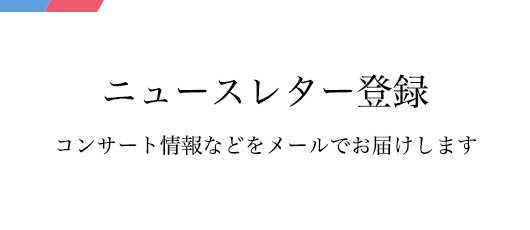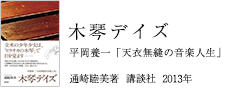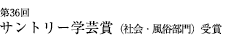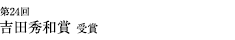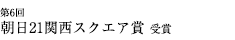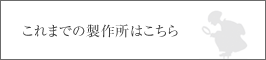杉本家で授業
21
今日は、毎年この時期恒例になった、京都の町家、重要文化財杉本家住宅で行われる京都女子大学の講義を担当させていただきました。
お座敷で、正座して聞く講義は、京都ならではですね。今日もいろいろ着物を持っていってみてもらいました。奥に見える床の間は、お正月のしつらい。この建物が建ったとき、まだ電気が通ってなかったので、この暗さはその当時を思わせてくれます。
お床には、円山応挙の軸がかかっていました。これまでの私の経験では、京都のお家で応挙の絵のあるような方は、その名を言う時「おうきょ」が「ド〜ソ」という感じで「きょ」の方にアクセントをつけられます。東京の美術館の学芸員さんにはありえない発音だと思います(笑)竹内栖鳳も「せ・いほう」と「せ」にアクセントではなく「せーほーさん」=「ド〜ド〜ミ」とのっぺり言われます。なぜか「さん」がついて、そこがアクセント。これを聞くと、京都に住んでいる私も「お〜、京都〜」と思います。
お茶を出していただきました。クリスマスのお菓子、うれしくなりますね。
今日は、前半が杉本家、杉本歌子さんのお話し。
昔は家で結婚式を挙げた、三三九度は夜に交わされた、めでたいからではなく暗いから金屏風があるのよ、そんな話は、女子大生にとっては「へぇ〜〜〜〜」の連続だったことでしょう。
歌子さんとは、同い年。
立派なお家を守って行かれるのは大変だろうと思いますが、なんだか最近ドンと構えておられて、すっかりオトコマエなおねえさん、という感じです。