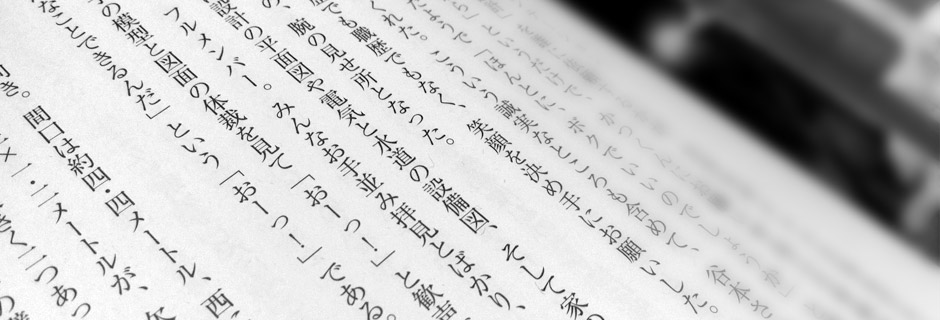
音楽家通崎睦美のもうひとつの顔、それが文筆家。もしかすると、書店に並ぶ書籍や、新聞、雑誌のエッセイで通崎睦美を初めて知ったという方も少なくないかもしれません。
アンティーク着物コレクションから京都の長屋の改装工事に至るまで、通崎睦美の目に映るものはすべて活き活きとした言葉になって綴られていきます。京都の細い路地を軽やかに駆け抜ける通崎自身のように、好奇心にあふれる文章をお楽しみ下さい。


消えゆく「京都の下町」が、ここにある。
──世界唯一の木琴奏者で、名エッセイストが書く「誰も知らない千年の都」
京都でも知られていない小さな町、それが「天使突抜(てんしつきぬけ)」。オシャレな名前に聞こえるけれども、古都の地場産業を支える職人さんが多く暮らす下町です。この町で、風呂敷職人の家に生まれた少女がプロの音楽家を目指すまでの物語や、さまざまな京都の人々との出会いを描く珠玉のエッセイ。


全米の少年少女は、「ヒラオカの木琴」で目を覚ます――
単身アメリカに渡り、ラジオのレギュラー番組を持ち、日米開戦の日まで10年9ヵ月、毎朝演奏を続けた日本人がいた。
世界一の木琴奏者・平岡養一、その一途な人生。
二人の演奏家の魂の交感が生んだ、音楽ノンフィクション。
<私が十歳の時に交わした、舞台上での固い握手。平岡が次世代に託そうとしたのは、木琴という楽器だけではなく、それを弾く心そのものだったのではないだろうか>――(本文より)
マリンバ奏者の著者は、「この木琴でしか弾けない」という曲の演奏依頼を受け、平岡の愛器と出会う。1935年製の木琴の音色に魅せられ、幼い日の舞台の記憶と共に、著者自らが扉を開ける『木琴デイズ』。
1907年(明治40年)生まれの平岡養一は独学で木琴を習得し、慶應義塾大学卒業後、わずか22歳で「木琴王国」のアメリカへ渡る。NBCの専属となり、毎朝15分のラジオの生番組に出演。日米開戦の日まで10年9ヵ月もの間、演奏を続けた。その間、ニューヨークのタウン・ホールでリサイタルを開催。世界一の木琴奏者の評価を得る。戦後の日本でも、NHK『紅白音楽試合』(『紅白歌合戦』の前身)に出演したほか、クラシックだけでなくポップスなど幅広いレパートリーを開拓。踊るような独特の演奏スタイルで日本人の心を捉え、国民的音楽家となっていく。著者は、そんな平岡の音楽人生を取材する過程で、自ら演奏するマリンバの「日本上陸」により、図らずも、木琴の時代が終焉を迎えたことを知る。さまざまな音楽的葛藤、癌との壮絶な戦い、巨匠が木琴に託した一途な思いを、音楽家の視点から描いていく。
通崎邸にあふれるキモノや楽器。その整理に困っていたところ、向かいの路地の長屋が売りに出された。住所は「天使突抜367」。あふれるモノたちを収納するため、築年数もわからない傾きかけた長屋のリフォームを決意。そこからてんやわんやの改修工事が始まった。集まったのは友人・知人のアーチストたち。彼らや町の人たちの交友を綴ったエッセイ。
「初めてマレットを持つ子ども達に、どうすれば自分自身も楽しく演奏しながら基礎的なことを教えられるのか」土肥寿美子さん作曲の厳選された30曲の練習曲に、谷本天志さんのかわいいイラストが添えられて、楽しいマリンバの練習帖が誕生しました。全曲先生と生徒が5オクターブのマリンバで連弾できるように書かれています。
アンティーク着物コレクターとしても注目を集めるマリンバ奏者・通崎睦美のユニークで魅力的なこだわりが詰まったフォトエッセイ集。日々に息づく「京ごころ」と「音楽家の感性」が満載。
デザインの楽しみがここにある。通崎睦美銘仙コレクション一挙公開!
アンティーク着物の一人者が、明治から昭和初期にかけて一世風靡した幻の銘仙着物柄100点を趣のあるエッセイとともに綴る美しい書。
これまでに掲載された連載やコラムを少しずつ紹介します。

各メディアに掲載された『木琴デイズ~』の書評や紹介文と、
関連コンサート「通崎睦美リサイタル 木琴文庫vol.2」のコンサート・レヴューです。

隔月で発行される、人気の親子で楽しむファッション誌『sesame』に、2005年の1年間連載させていただいた「通崎睦美のKYOTOアート散歩」。
登録された子どもモデルのファイルから、あれこれ悩んでモデルさんを指名するところからスタート。撮影現場では、子どもといえどもさすがに「プロはプロ」と感心したものです。
アートディレクションは谷本天志さん。

以前音楽欄を担当されていた記者、千葉淳一さんからのご依頼で、連載を書かせていただきました。
テーマは、いろいろ相談した結果、現代京都の「着る物」について。
今和次郎が提唱した「考現学」をいただいて「着ることの〜京都考現学」としました。
ちょっとタイトルが堅いということで、谷本さんにかわいいイラストをお願いしました。
まだ、文章を書き始めたばかりの頃。取材対象の方とカメラマンとスケジュールを合わせて取材して、一週間に一度文章を仕上げるのは初めての仕事。それだけで、目が回りそうでした。
ちなみに、千葉さんは日経を退職され、現在はギャラリスト、橘画廊のオーナーとして現代美術展の企画をされています。